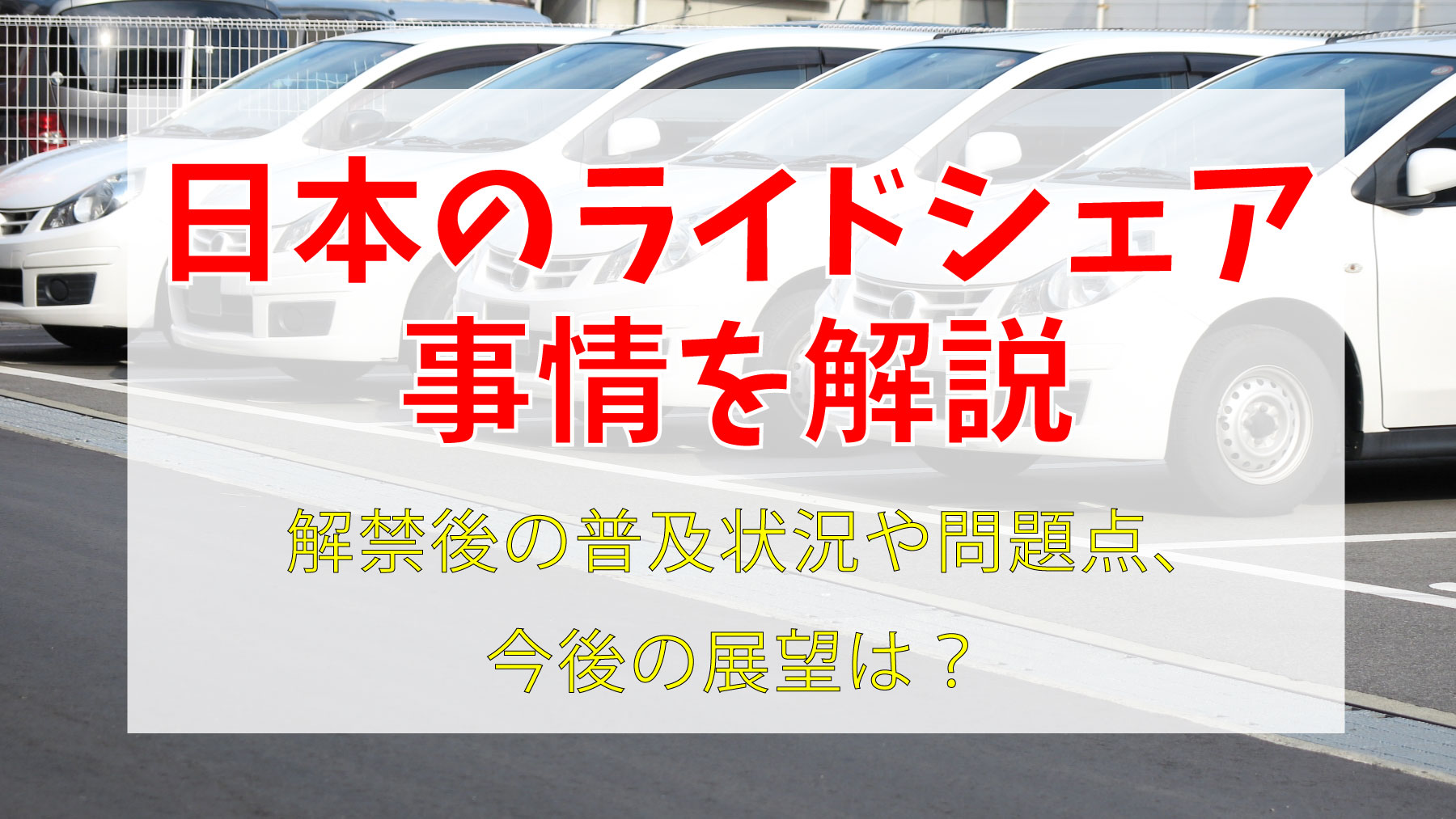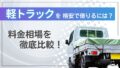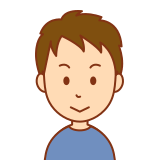
「ライドシェアは日本で使えるの?」
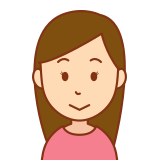
「タクシーやカーシェアと何が違うの?」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?海外ではすでに一般的となったライドシェアですが、日本では制度や法律の制約があり、まだ発展途上のサービスです。
そこで本記事では、日本のライドシェアの現状や仕組み、料金、利用方法をわかりやすく解説し、海外との違いや今後の展望まで丁寧に紹介します。
日本版ライドシェアの現状は?

日本におけるライドシェアの現状は、海外のように自由に誰でも参入できる形ではなく、国土交通省の管理下で限定的に導入されています。
日本では、自家用車を使ってお金をもらって客を運ぶ行為(白タク行為)は道路運送法により禁止されているため、基本的にはUberなどの大手プラットフォームも、日本ではタクシー事業者と提携する形でサービスを展開するしかなく、本来の「個人がドライバーとして気軽に登録し、収入を得るモデル」という形では実現されていないのです。
そのため日本版ライドシェアは都市部での普及がなかなか進まず、地方の交通手段不足を補う役割が中心です。とはいえ、日本版ライドシェアは将来的な社会課題の解決策として期待が寄せられています。
ライドシェアとタクシー・カーシェアの違い

ライドシェアとはいえ「タクシー」や「カーシェア」との違いを知らない方も多いのではないでしょうか。ライドシェアは、タクシーやカーシェアと混同されがちですが、仕組みや利用シーンに明確な違いがあります。簡単に整理してみましょう。
| サービス | 運転手(免許) | 料金体系 | 利用方法 |
| ライドシェア | 一般人(普通免許) | アプリで変動 | アプリでマッチング・決裁 |
| タクシー | プロの運転手(二種免許) | メーター制or定額 | 街中で拾うor電話・アプリ予約 |
| カーシェア | 自分で運転(普通免許) | 時間単位での貸出 | 専用車をアプリ・Webで予約 |
「タクシー」は、運転のプロである二種免許保持者が乗客を輸送し、メーター制で料金が決まるのが一般的です。一方で「カーシェア」は、自分で車を運転するため、移動サービスというより「車の貸し出し」に近い性質があります。
そして「ライドシェア」は、アプリでマッチングした一般ドライバーが乗客を目的地まで運ぶ仕組みです。
このように、三者はそれぞれ「運転を誰が担うのか」という点で大きく異なります。
日本版ライドシェアの仕組みと利用方法

日本版ライドシェアは、2024年に国土交通省が制度化した「自家用車活用事業」により誕生しました。背景には、都市部でのタクシー不足やドライバー高齢化など、慢性的な人手不足の問題があります。
そしてこの制度では、一般ドライバーが自家用車を使って乗客を運ぶことを認める一方、運行管理は必ずタクシー会社が担う仕組みになっています。つまり、海外のように個人が自由にドライバーになれるわけではありません。安全管理と信頼性を確保する“日本独自のライドシェア”といえますね。
また、利用方法は非常にシンプルで、スマートフォンの配車アプリ(例:「GO」「S.RIDE」など)を使って対応エリア内で車を呼ぶだけ。料金はタクシーとほぼ同等で、支払いはキャッシュレス決済が基本です。現在は全国47都道府県すべてで導入が進み、安全性と利便性を両立した日本独自の移動手段として、ますます注目を集めています。
日本版ライドシェアのメリットとデメリット

日本版ライドシェアの最大のメリットは、交通手段が不足する地域で新たな移動手段となることです。過疎地ではバスやタクシーの運行本数が限られるなか、住民の通勤や通院、買い物などを支える重要なサービスとして注目されています。
また、タクシー会社の運行管理のもと、二種免許を持たない一般ドライバーが運転できるのも魅力。副業や短時間勤務など柔軟な働き方が実現できます。
一方で、安全確保や事故時の補償体制などはまだ発展途上であり、ドライバー教育や利用者の安心感をどう確保するかはまだ改善の余地があるといえるでしょう。とはいえ、地域の交通課題と働き方の多様化を同時に解決する新しい仕組みとして、今後の発展が期待されています。
日本と海外のライドシェア比較と今後の展望

海外ではUberやLyftなどが一般的で、誰でもアプリに登録して自家用車で乗客を運べる自由な仕組みが主流です。料金は需給に応じて変動し、利便性が高い反面、安全面のトラブルも報告されています。
一方、日本版ライドシェアはタクシー会社の運行管理を前提とし、ドライバーの登録審査や保険制度を厳格に運用している点が大きな違いです。安全性を最優先に制度が整備されているため、利用者が比較的安心して利用できる環境が特徴といえます。
今後は、地方での交通空白地の解消や都市部での深夜帯運行など、社会課題の解決に向けた活用がさらに進むでしょう。AIによる最適配車や自動運転との連携など、テクノロジーとの融合も期待されており、日本独自の安心・安全なライドシェアモデルとして世界に広がる可能性もあります。
日本版ライドシェアに関するよくある質問

日本ではライドシェアは完全に解禁されたのですか?
現時点で日本におけるライドシェアは完全には解禁されていません。基本的に自家用車を使って収益を得る運送(白タク行為)は違法とされており、国が認めた特定の制度や条件のもとでのみ可能となっています。主にタクシー不足や地域交通維持のため、限定的に導入しているのが現実です。
日本のライドシェアはどこで利用できますか?
現在、日本版ライドシェアは全国47都道府県すべてで導入されています。都市部ではタクシー不足の解消、地方では交通手段の確保を目的に運用されています。
日本のライドシェアの利用料金や支払い方法は?
日本版ライドシェアの料金は基本的にタクシーと同じ水準で設定されています。海外のように極端に安い料金が適用されることは少なく、既存のタクシー料金に準じるケースが一般的です。支払い方法はキャッシュレス決済が中心で、クレジットカードやスマホ決済サービスが利用できます。
日本のライドシェアは誰でもドライバーになれますか?
日本では誰でも自由にライドシェアのドライバーになれるわけではありません。海外では自家用車を登録するだけで参加できる仕組みが一般的ですが、日本ではタクシー事業者が運行管理を担い、登録や安全管理を厳格に行っています。そのため、自治体や事業者が定める条件を満たさなければドライバーとして活動できません。
まとめ
日本版ライドシェアは、海外のように誰もが自由に参加できる仕組みではありませんが、2025年現在は全国47都道府県すべてで導入が進み、安全性と信頼性を重視した日本独自の形として全国に広がりつつあります。
また、二種免許を持たない一般ドライバーでも働ける仕組みが整い、副業や短時間勤務など柔軟な働き方を支える点も注目されています。一方で、安全確保や補償体制、料金の公平性といった課題も残されており、制度の成熟にはまだ時間が必要です。
とはいえ、日本版ライドシェアは「便利さ」と「安心」の両立を目指す新しい社会インフラとして、今後の交通のあり方を大きく変えていく存在になるでしょう。

全車ETC付き。1週間・1ヶ月単位なら中長期レンタルがお得。1日あたり800円から!Webで実際のレンタカーの写真や走行距離を確認でき、待ち時間ゼロで24時間いつでも予約可能です。もちろん1日単位のレンタルも大歓迎!大阪・東京・兵庫に店舗を構える「業務レンタカー」の魅力は、圧倒的な安さにあります。ぜひ大手レンタカー店と比較してください。
「気軽に、レンタカーを利用してほしい」「レンタカーでより便利に、豊かに暮らしてほしい」との思いでこの業界に携わって、早20年。これからも多くの方に、“快適”と“感動”を与えるサービスを提供いたします。
\☎050-5434-5050/
田川 英紀
最新記事 by 田川 英紀 (全て見る)
- ライドシェアの問題点とは?日本で普及しない理由と安全性の課題を解説 - 2026年1月12日
- ライドシェアとタクシーの違いを徹底比較|料金・安全性・働き方の違いを解説 - 2025年12月16日
- 福岡県のマンスリーレンタカー10社の料金を徹底比較!格安で借りられるのはどこ? - 2025年12月1日